哲学者である苫野一徳さんの著書『はじめての哲学的思考』は哲学的思考の入門書です。
哲学的思考であって、哲学史ではないところに注意が必要です。
哲学史の入門書でおすすめなのは飲茶さんの『史上最強の哲学入門』ですが、哲学的思考の入門書は苫野さんの『はじめての哲学的思考』がおすすめです。

『はじめての哲学的思考』の概要、要点をまとめていきます!
哲学はどのような学問か?
哲学を学ぶ以前の問題として、哲学とは何かが人によってかなり違うという問題があります。
著者の苫野さんは「哲”学者”」ではなく「”哲学”者」を目指すようにすすめています。
つまり、〇〇年に□□が「□△◯□△◯」と言ったという研究対象的な学問として哲学を捉えるのではなく、自分で考える、哲学するという意味で哲学を捉えるということです。
哲学するには哲学的な思考を身につけることが欠かせません。
この哲学的な思考は哲学だけでなくビジネスや教育など様々な場面で役に立ちます。
安斎勇樹さん、塩瀬隆之さんの著書『問いのデザイン: 創造的対話のファシリテーション』では『はじめての哲学的思考』を引用してファシリテーション技術として哲学的思考法を紹介しています。実例として様々な場面で哲学的思考法が活用されている様子も見ることができます。
『はじめての哲学的思考』を読めば、哲学は暗記科目のようなものではなく、自分で考える学問だということがわかります。
『はじめての哲学的思考』の概要
『はじめての哲学的思考』は三部構成になっています。第一部ではそもそも哲学とは何なのか、哲学がどのように役に立つのかが解説されています。
そして、第二部で具体的な哲学的思考の奥義を、第三部でその実践の場として哲学対話が紹介されています。
私が普段行っている哲学対話はこの第三部を参考にしています。
ここでは本書の「第一部 哲学ってなんだ?」の概要をかいつまんで紹介してみます。
第一部 哲学ってなんだ?
このパートではそもそも哲学とは何かが解説されています。
現代の民主主義に至るまでに哲学者がどのように貢献してきたのかを振り返りながら、哲学は役に立つことを示しています。
「哲学は役に立たない学問」という固定観念を持っている人にとっては衝撃かもしれません。
そして、宗教、科学と比較して哲学とは何かをわかりやすく解説しています。
宗教との違いは以下の通りです。
いくら聖書を読んだところで、その事実をたしかめることはできません。しかし、哲学であれば思考することでたしかめることができる。たしかめることができなければそれは哲学とは呼べません。
でもたしかめ可能性で言えば、現代では科学が一番ではないかという疑問が湧いてきます。
苫野さんは科学と哲学では明らかにする領域が異なると言います。
科学が明らかにするのは、いわば「事実の世界」のメカニズムだ。それはたとえば、(中略)人は恋をしている時、脳の腹側被蓋野が活性化しているとか、フェニルエチルアミンやドーパミンが分泌されているとかいった、文字通り「事実」の世界だ。
それに対して、哲学が探究すべきテーマは、〝真〟〝善〟〝美〟をはじめとする、人間的な「意味の世界」の本質だ。 「〝ほんとう〟のことってなんだろう?」「〝よい〟ってなんだろう?」「〝美しい〟ってなんだろう?」そして、「人生いかに生くべきか?」
こうした意味や価値の本質こそ、哲学が解き明かすべき問いなのだ。
そして哲学が探求する「意味の世界」は科学が探求する「事実の世界」に原理的に先立ちます。なぜなら、人が何に価値を見出すかによって、何を”事実”として認識するかが決めるからです。
技術が高度に発達した現代では、倫理的な問いに答える必要あります。これは「意味の世界」の領域です。今こそ哲学は科学の行く先を指し示す必要があると苫野さんは述べています。
まとめ
私は『はじめての哲学的思考』を読んで、哲学に対する認識が全く変わりました。
哲学が役に立つ学問であったこと、どのように実践すれば良いのかここまで、わかりやすく解説した本は他にないと思います。
ぜひ哲学的思考の一冊目としてご一読することをおすすめします!
|
|
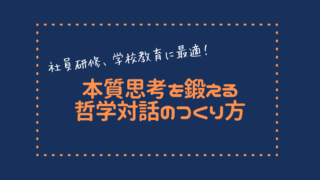
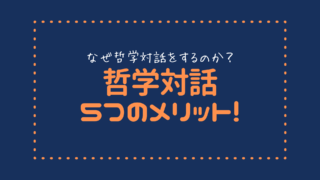
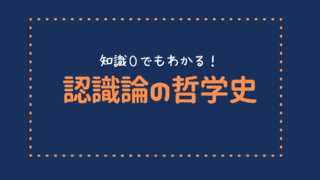
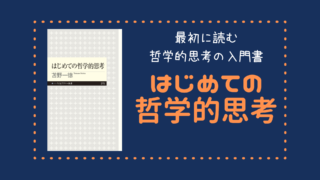
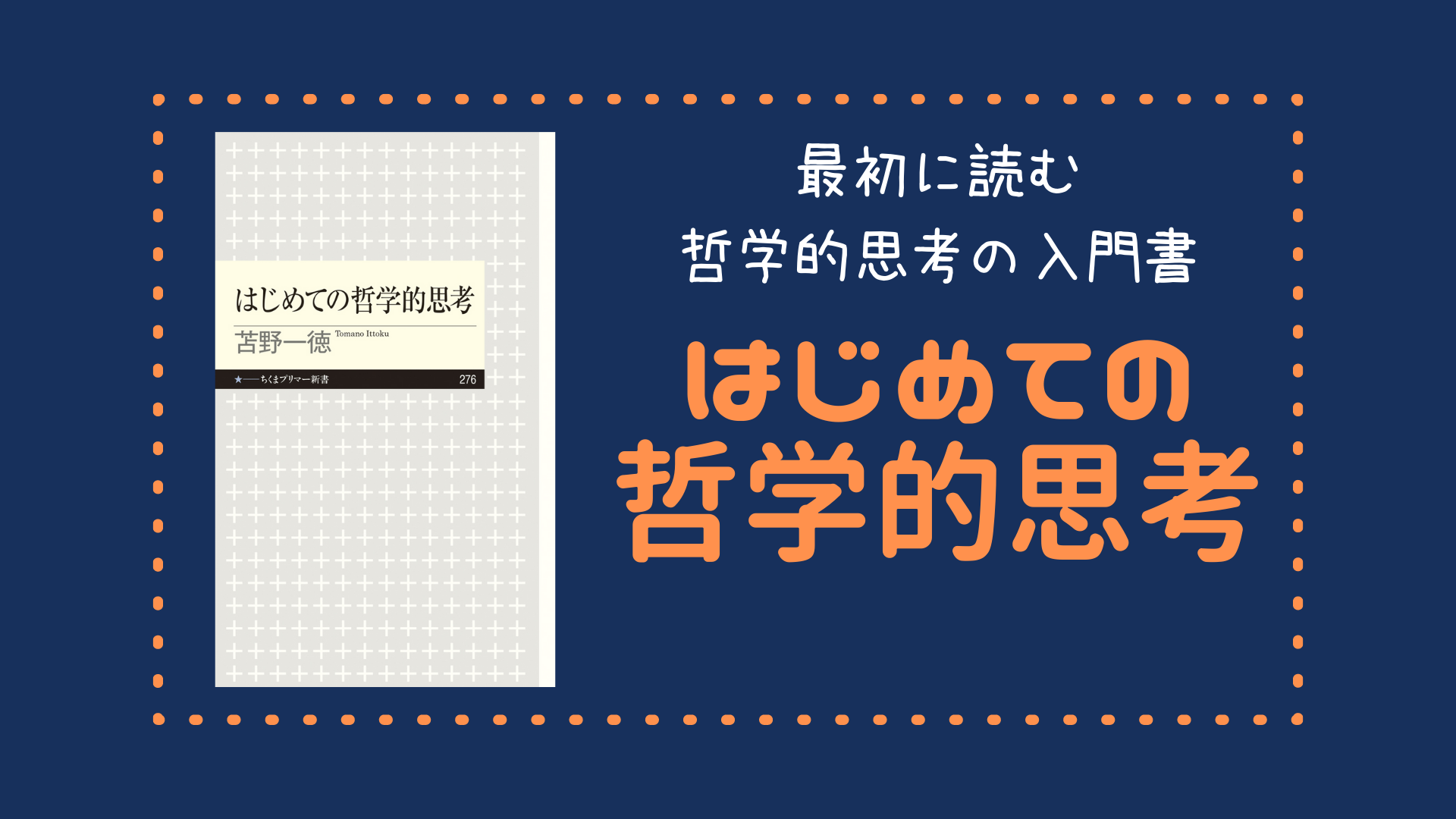




コメント